令和7年7月に開催された川越市医師会の「継続看護発表会」において、当院の褥瘡対策委員会が発表を行いました。
そこで、発表を担当した3名の委員の皆様との懇談会を企画しました。特別ゲストとして、褥瘡委員会・委員長の医師 M先生(病棟主治医)にもご出席いただいたので、発表後の感想や委員会活動の様子などをお聞きしてみたいと思います。
発表のテーマは『多職種連携を意識した褥瘡対策委員会の活動』
褥瘡対策委員会・議長の I さん(病棟師長) が発表を担当
書記の A君 (リハビリテーション科・副主任 理学療法士) が資料作成と質疑応答を担当
病棟委員の Wさん(看護師)が原稿作成と発表サポートを担当
ーー まずは発表を終えたところでの率直な感想をいただきたいと思います。
I さん やっぱり大勢の中で発表というところでは、かなり緊張しました。ある程度時間どおりに発表はできましたが、先生はじめ、Aさん、Wさんのサポートがなければ、多分まとまっていなかったな、って思います。

Wさん 今回、発表原稿を作るにあたって、「多職種」というところをどのように伝えていくか、が大変でした。作っていく中で、普段も感じていることではあったんですけど、他の職種なしでは看護の力も発揮できないし、褥瘡も良くならないし、ということを 改めて 感じ、それを今回なんとか皆さんにお伝えできたのかな、と思いました。
A 君 理学療法士個人として発表するっていうのは今までにもあったんですけど、今回のように先生にも資料を見ていただいて、法人内の看護師さん、多職種の皆さんと一つのものを作り上げる、という事は、初めての経験でした。非常にやりがいがある仕事だったな、というのが終わっての感想です。
ーー ありがとうございます。先生は、発表リハーサルの時にお越しいただいたと伺っていますが、どのような感想をお持ちでしょうか。
M 先生 いわゆる学会発表なんかだと、病院紹介から入るって普通ないんですよ。そういう病院紹介から始まるという構成でしたが、少子高齢化で高齢の方が増えてきて、それで寝たきりになる人が増えて、床ずれみたいになる人が増えて、要するにそういう時代の要請と、当院の置かれている環境っていうんですかね、療養型病院とか川越市という立地とか、そういう社会的要因と当院が繋がる一つのストーリーっていうのかな、多職種連携の必要性に繋がる流れみたいなものを、ああ、なるほどと感じながら聞いていました。褥瘡というテーマが病院紹介とも重なり、病院としてのメッセージ発信という点でも非常に意義があったと思います。
ーー 他の病院さんは、どんな発表だったのですか?

A 君 ええと、うち含めて4チーム発表がありまして、「看護補助加算について」、「消防士の人が看護師を目指した話」、あともう一つ「言語聴覚士が1名入職したことでもたらした口腔ケアに関する環境」、みたいな感じでした。
―― どれも聞いてみたいと思わせるテーマですが、当院は病院の特性に合わせた切り口で、具体的な症例などもあり、ひときわ印象に残る発表であったように思います。質疑応答などはいかがでした?

A 君 私は質疑応答の部分で力になれればと思いまして、準備をしていました。耐圧分散に関するちょうどいい質問が来まして、答えられる範囲だったこともあり、うまく対応できたと思います。
ーー 他に発表で何かご苦労されたことなどはありますか
Wさん 文章の、表現の仕方ですね。発表用の。
I さん 私も同じくですね。Wさんの原稿のお陰で、当日の発表は、まあなんとかなったって感じです。
A 君 資料の作成を担当したのですが、スライドの構成が難しかったです。発表の場は、看護師さんが沢山いらっしゃるということで、理学療法士と看護師さんでは、若干見るポイントが違ってくるだろうとなと。会場の皆さんがどういうことを聞きたいのかとか、どういうことをスライドに乗せると入っていきやすいのかとか、すごく考えました。
ーー なるほど。まさしく今回の発表テーマが「多職種連携」ということでしたが、普段の委員会活動においてはいかがでしょうか?

I さん M先生が褥瘡委員会を担当されるようになって、褥瘡回診を実施するようになりました。その中で、看護部やリハビリテーション科の他にも、薬剤師さんや管理栄養士さん、あるいは医事課長さんといった多職種の皆様との連携が深まっていったと思います。
Wさん リハさんが結構協力的で、何に関しても関わってくれるので、すごくやりやすいと感じています。言いやすいので、つい頼っちゃうんですけど、言いやすい環境ってすごくありがたいなと思います。
A 君 リハビリ科としては、日々の変化を、看護師さんにもしっかり伝えていくっていうのがまず大事なのかな、というのは思っています。リハビリ科の中で何かやっていることを完結させるのではなくて、いいことがあったら看護師さんとか先生にも、この人こういうふうになってきていますよ、って言った方が絶対いいですし、何か課題があるならそれは相談した方がいいですし。そういうコミュニケーションがないと、なんか褥瘡ができそうだとか、できてしまった時に、ちゃんとした対応ができないと思います。普段からコミュニケーションをとっておくことが、結果的に褥瘡における多職種連携を機能させ、質の高いものを提供できることに繋がるのかなと思います。

ーー 今後の委員会活動の抱負などありましたらお聞かせください。
I さん 褥瘡は作らない、っていうのが勿論一つあるんですけど、見つけたりとか、発見したりとか、そういうのがあったら早期に直す、早期対応して治癒ができる、っていうのを常に目標に置いておきたいなとは思っています。
Wさん 委員会の中でも、褥瘡がもう完治しましたっていう事例もあるので、そういうのをぜひ他の病棟でも共有してもらって、他の病棟も頑張っているからうちも頑張ろう、みたいなことを、委員として引き続きやっていけたらいいなと思います。
A 君 褥瘡に対して危機意識を持つスタッフがずいぶん増えたと思うんです。ただ、まだ十分じゃないスタッフもいると思うんですよ。そこをどうやって底上げしていくのか。委員会に参加してない人にもやっぱり知ってもらいたいし、リハビリの若手のスタッフも、ちゃんとその辺を意識してやってほしいし、そういうところの育成も委員会に求められているのかな、と思っています。
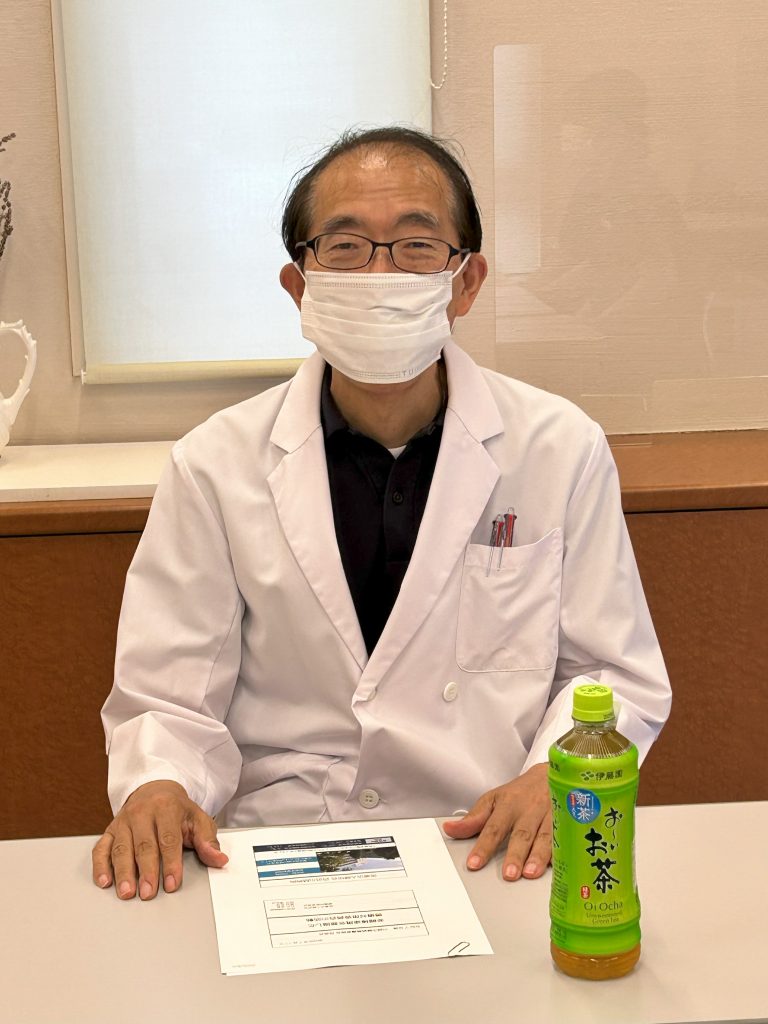
M 先生 今話に出たように、危機意識は変わってきましたね。昔は、持ち込まれたもの含め、悪くなってしまった褥瘡を、先生お願いします、という感じでね。でも今は、こういう状況でここまでできているので先生確認してください、といったように、初期対応、早い段階での対応がすごく良くなってきたと思います。
あと、当時も多職種連携をしなければ、という意識はあって、ポジショニングの指示を写真でベッドに貼ったりとか工夫はしてくれていたんだけど、使う用具の名称の統一性がなかったりとか、コミュニケーション的な部分でも追い付いていなくて。でも今は多職種連携が、それはもう常に当然のことになっていて、よくなったらみんなに、成功っていうか、よかったねっていう感じで、そういうのを分かち合えるみたいな状況になっています。だからこそ初期対応もできている、ということだと思います。
ーー 素晴らしい! 先生に上手くまとめていただいたところで、お開きとしたいと思います。ありがとうございました。
~当院の褥瘡の取り組みは、病院公式ホームページにも特集記事があります。
こちらからご覧ください! ↓
https://www.seibukawagoe-hp.or.jp/bedsore




